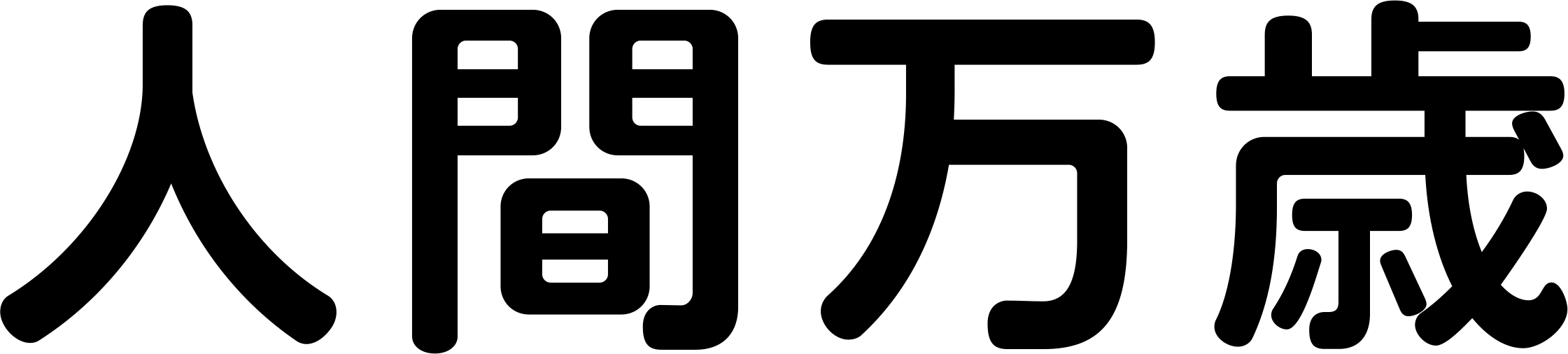おじさんだって綺麗
嘆くおじさんたちの昼休み
娘「ねぇ〜、洗濯機に入れないでって言ったじゃん!マジで終わってる」
本藤「…。」
若者「おっさん金持ってねぇの?財布落として電車乗れないんだよねぇ。五千円くれや」
川上「あっ…じゃあこれ…。」
女社員A「西山のことセクハラとパワハラで上長報告する?笑」
女社員B「むしろスメハラの方が信憑性高いよ、上長も分かってるだろうし笑」
市浜「…。」
昼下がりの下町。油が跳ねる音と、ラジオから流れる演歌のサビが中華屋の空気を支配していた。
午後1時。酢豚定食が2つ、麻婆豆腐定食が1つ、麦茶が3杯。そして、黙ってスープを啜るおじさんが3人。
「今日また、娘に怒られましてね」
と、本藤が口を開いた。手元のレンゲをいじる指が、どこか所在なかった。
「洗濯物、一緒に洗わないでって言われたんですよ。寝ぼけて出しちゃった自分も悪いんですけど、そこまで怒らなくてもねぇ。なんか…悲しいもんですよ。お父さん、しょんぼりです」
川上は笑いながらも、どこか気まずそうに言葉を選んだ。目線をスープに落としたままだった。
「リンちゃんでしたっけ、高校生でしたよね。難しい年頃なんでしょうけど、本藤さん職場じゃ“元気印”って呼ばれてるくらい慕われてる人なのに、家庭での扱われ方ちょっと落差ありますよね」
「いやいや、慕われてるなんてそんな。…でも、娘に嫌われるっていうのはね、効きますよ。じんわりと」
本藤は、レンゲを置き、箸を両手で握って小さく息をついた。
「“誰のおかげで飯食えてんだ!”って、ドラマでよくあるじゃないですか。あれ、言わないんです?」
市浜が、ちょっと楽しそうに言う。麻婆豆腐の豆腐をすくいながら。
「言えるわけないですよ。そんなこと言ったらたぶん、一生口聞いてくれなくなります」
と、本藤。
「自分が仕事してお金稼いでるのは娘のためですから。恩着せがましい態度とは真逆です。娘に飯食わせたいがために仕事してるんで。『誰のおかげだ!』って言い出したら、それは目的と行動が逆になっちゃいますよ。イヤイヤ娘を育ててるわけじゃないんです」
沈黙が少しだけ流れたあと、川上が言葉を足した。箸先が酢豚の上を空振りしていた。
「……人のために給料を稼ぐって感覚、僕にはまだないなあ。独り身ですし、自分で稼いだお金は自分で使いたいですよ。でも……」
唐突に言いよどんだ川上の眉間に、うっすらシワが寄った。彼は顎をさすりながら言った。
「今日また、あの駅の2人に絡まれたんですよ。『おっさん財布落としたから五千円くれ』って。自分に使うどころか知らない誰かに使われてます」
「え?また?怖いっすよあの2人。次は自分かもしれませんわ」
と市浜。顔をしかめて、スープの器を両手で持ち上げた。
「……我々おじさんって、弱いんでしょうか」
本藤が静かに、しかし確かな声で言った。テーブルに置かれた麦茶のグラスが、少しだけ揺れた。
「若い子に絡まれて笑われて、家では煙たがられて。もうおじさんってだけで“負け”みたいな空気、あるじゃないですか。世の中的には“モブキャラ”みたいなもので、名前と人格を与えられていないような存在」
「負けって言い方は極端ですけど、実際ちょっと思うところあります」
川上は苦笑しながら続けた。箸を回す手が止まらない。
「さっきも社内の休憩スペースでユカマナのコンビが西山さんのこと、セクハラとかスメハラとか言ってクビにしようぜって話し合ってるの聞こえてきましてね」
「え、西山って、あのガタイの良い、経理の人っすか?」
「そうです。僕らからすれば、ちょっと昔気質だけど良い兄貴分じゃないですか。でもあの2人からしたら目の敵らしくて、あの2人が怖がってる演技しながら上長に報告すりゃ上長も無視できんだろ。上長に西山肩トントンされると思うけど、自分は証言して絶対守ろう思ってるんですよ。にしても怖かったです、あれは」
「“ハラスメント”って言えば男を簡単に潰せると思ってる節、あるっすよね。フェミニスト怖すぎ」
市浜は、まるで天気の話でもするかのような調子で言った。
「フェミニズムって本来“おじさんおばさん若人も、すべての人が平等に扱われるべき”って理念だったはずでしょ。なのに今は、若さと見た目が武器になって、おじさんだけが敵扱いされてる気がします」
「……おじさんって、ゴキブリと一緒ですよ」
と、本藤。
「そこにいるだけで、なんか嫌がられる」
「自虐がすぎますよ」川上が苦笑する。
「全おじさんが嫌われてるわけじゃなくて愛されてるおじさんもいるじゃないですか。なんかで読んだんですけど、おじさんが嫌われる主な原因はコミュニケーションが下手ってのがあるらしいです。おじさんは若い子と早く距離を詰めたいがために下の名前で呼んだり、焦って馴れ馴れしく接してしまったり。でもそれは若者からしたらそれこそ馴れ馴れしいなとか舐めてんのかとか近づこうとしててキモいって感じるんですよ。実際例えば同年代の取引先の方々をいきなり下の名前で呼ばないじゃないですか。向こうの出方を伺ってから距離測るじゃないですか。我々は若者との距離感を掴むのが下手みたいです。というより若者を下に見てるのが透けて見えてるんですよね。そりゃ嫌われますよ。反省すべきはおじさんでした。」
彼はポケットからスマホを出しかけたが、やめてまた仕舞った。
「わー、身に覚えがあるかも…。自分は被害者かと思ってたらまずの加害者が自分でしたってパターンでした。
でもそれは近しいおじさんが嫌われる理由ですよね。もっとなんて言うんだろ。主語の大きい「おじさん」の世間からの評価が低いんじゃないかって思うんです」
と市浜が言った。肩に力が入っていた。
「一番厄介なのは“おじさん”というだけで人格ごと記号化されることですね」
と本藤が呟いた。彼の視線はテーブルの縁に落ちていた。
「我々おじさん達が積み上げてきた時間や仕事の成果が、見た目や年齢だけで切り捨てられるなんて。“おじさん”って記号にすべてを押し込められるなんて、ちょっと…切ないですよ」
と市浜。
「そうですね、川上さんが親父狩りされたみたいに、そもそもおじさんが“弱いもの”として見られてる節があります。でも、我々はもうどうしようもないおじさんじゃないですか。肯定的に、胸張って“おじさん”って名乗れるようになりたいですよ」
と本藤は言った。
「だって、おじさんになる、歳を取るって、悪いことばっかじゃないですしね。
恋愛とか欲とかから少しずつ解放されて、他人の目をそこまで気にしなくて良くなる。だらしない上裸で海岸に寝そべったって、それもまた自由。がめつくなったっていいじゃないですか、若者だって、いずれはこっち側に来るんですよ。歳を取るのは、誰にも避けられない道なんですから」
誰が言ったかは分からない。
麦茶の氷がカランと音を立てた。
中華屋のラジオから、再び演歌のサビが流れた。
人生いろいろ、男もいろいろ、女だっていろいろ。
そして、おじさんだって、綺麗なのだ。