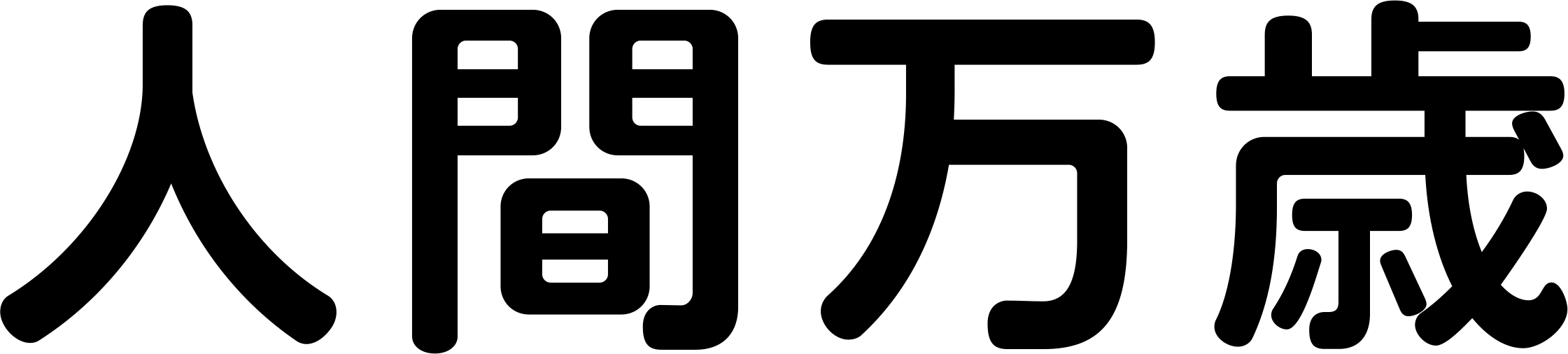赤ちゃんかけっこレース
かけっこ大会
営業第三部の次長に推薦された。七年という歳月が営業部で私を磨き、あれこれと勘繰らせてきたが、遂に、選ばれたという事実が静かに私の胸に落ちる。口では淡々と言い繕えるが、内面では不意に膨らむ優越と、同時にしぶとい罪悪感がせめぎ合う。
私は長年、部下の面倒見が良い、融通の効く、話しやすい上司を演じてきた。演じる、という言葉がふさわしいほどに。トラブルが起きれば根回しを買って出て、事を荒立てずに穏便に済ませるコツを身に付けた。今はどんな問題であれリカバリー出来ますと言い切れる程には自信がある。その自信は油断のない夜の数と、失敗をあらかじめ想定した事前検死の積み重ねの賜物だ。上の自慢話にはすぐに乗っかり、思う存分おだてて彼らの顔を立てるコバンザメのような後輩を演じ、恥ずかしながらゴマをするマネも何度もしてきた自分。そうした演技が、人心を掌に収める技術となり、私の道具箱を満たしていった。
休日と称して、法定休日には楽しくもない興味もないゴルフに赴き、「社長さんお願いしますよ〜」と何度もぎこちない笑顔を振りまいた。あの笑顔は私にとっては芝の上の仮面であり、同時に私を形作る儀式でもあった。おかげでアマチュア程度のゴルフスキルが身についてしまったが、それもまた、名刺と握手と薄笑いの中で換算される「価値」の一部に過ぎない。
仕事の現場では、私は誰よりも退勤時間を遅くし、自分なりに頑張ってプロジェクト進めてます感、進捗管理が大変ですけどなんとかやってます感をアピールしてきた。実際、淡々と悪くない成果を積み上げてきたことは事実だ。だが、昨今はコンプライアンスや社内規則が厳しくなり、大それた真似はできない。入社時や営業先では、それはまぁ規範意識の薄い手法に何度も手をかけてきた。あの時の成果があるからこそ今この席に座れていると理解はしているが、もし部下が同じような真似をしていたら自分は指導するのだろうと、自省の念が胸の奥でくすぶる。取引先との談合で話を進めてから稟議書提出、巻きでの社内決裁なんてのは社会舐めてんのかって話です——と、私自身は声高に否定するが、その否定には過去の自分への言及も含まれている。
実際、同期の中では一番早い出世なのが大変に優越感を味わわせる。同期には弥山と尾原がいたが、彼らは今どこで何をやってるのだろう。弥山は三年前だったか、部下へのセクハラかパワハラか何かで総務へ異動になったんでしたっけ。尾原は五年前に母親が倒れて看病をしなくちゃいけないとか何とかで福井支店長になりましたか。出世レースでは私の勝ちですね。
そんな小さな勝利の宣言が、夜の一杯の酒の味を甘くする。
だが、私はふと立ち止まり、問いを立てる。私はいつから競争しているのだろう。
今は、出世が早い方が勝ちのレースをやっていて、それは人が羨ましがる大企業への就活レースで、人よりも目立ち周りの奴らを言葉でねじ伏せ、優秀そうに見せることができたからである。その「チケット」はどこで入手したのか。小学校、中学校、高校生のときに、隣の席のやつよりも、クラスのどいつよりも、学年の誰よりも、同年代の知らん奴よりも必死に勉強して正解を当てまくったから手に入れられたチケットだ。だが更に遡れば、そのチケットを買っても良いと親に思わせるために、姉を悪者にして弟を蹴散らし、親に子を育てる喜びを与えて、育った子を自慢できるくらいに愛を注がせる喜びを与える代わりに保護を受けられたから買えたチケットである。買うためには父親の精子達1億の中から最初に卵子に辿り着かなければならなかったわけで、で実際に自分は1億のどれよりも最初に卵子に辿り着いたんだ!この荒唐無稽にも聴こえる比喩が、私の内側にある「勝利の系譜」を物語る
私は、命を宿す前、精子の頃から勝ち続けてきた。ずっとずっと勝ち続けてきたんだ!流れに身を任せる一匹の細胞が、運と瞬発力で勝ち抜いたその瞬間から、私の物語は始まっている。1億分の受精競争に勝ち、家族の序列で最上位を確保し、受験戦争で雑魚を蹴散らし、就活でボンクラを踏み台にし、出世街道ではど真ん中を歩いている!
そんな自負は、時に誇大妄想の香りを帯びるが、それが私の生き様の中心であり続けるのも否めない。
趣味?友達?世帯を持つ?子を産む?そうですか、それらにも幸せがあるよって諭されたが、そんなわかりきったこと言うなよ。そこにも幸せがあるってのはそりゃ当然だろ。彼らの視線において目に見える幸せだからこそ幸せだって言ってるんだろ。だが私には違う形の希求がある。であればだ、誰よりも出世してふかふかの椅子に座りながらコーヒーを飲む、にも幸せがあるんじゃないのか?少なくとも私にとってはそれが人生での究極の幸せであり、生まれてきた人間にとっての最終目標だと信じてる。資本主義の国で生まれて育って生きているのであればその夢を持つことは何ら不思議ではないだろう。
「好きなことで生きていく」—素敵なキャッチコピーだ。私に当て嵌めれば「優越感で生きていく」。
その言葉は決して軽薄ではなく、私の胸に正直な響きを残す。戦おう、競おう、レースをしよう。そして私が勝つ。
その宣言は虚勢かもしれないが、同時に私が己の存在理由を掲げる最も率直な言葉でもある。
出世して偉くなるのが私の夢。
そう心から思えれば良いものを、なんだかモヤモヤするのはなぜだろう
常に頭の隅にあって、考えそうになると無理に押しやっていたあの問いが湧き上がってきた。
このレースには果たしてどこにゴールがあるのだろうか。何を成し遂げれば終わりだと告げられるのだろう。私はいったいいつまで走り続ければ良いのか。いや、そもそもいつからスタートしていたのか。誰が号砲を鳴らしたのか。なぜ私はこのレースに参加しているのか。どこの誰がレースに参加しているのか。
競っているが、競っているのか?。
いや、もしかすると「レース」など存在しないのかもしれない。ただ前へ進んでいるだけで、それを他人が勝手に競争と呼んでいるだけではないのか。
私はなんでもない位置に立たされたが力なく座ってしまう、周りの人が拍手でおだて、それいけと声を次々にあげている。スタートラインがどこにあり、どれほどの距離と時間が用意され、どこにゴールが待つのか——。
そんなことは何ひとつ分からない。分からぬままに足の内側を滑り止めに膝と手のひらを動かし、息を切らせ、ただ走っている。
なぜ走っているのかも分からない。けれども私の胸奥にふと浮かぶのは、いや、向かっているのは、ただあの場所で両腕を広げ、微笑みながら私を見つめて待っている母の姿だ。母の声に呼ばれ、母の温もりに触れたいがために、私は走っているのかもしれない。勝敗や順位や名誉ではなく、ただあの原初の安らぎに辿り着きたい——。
そう願う心が、いまも私の足を動かしている。