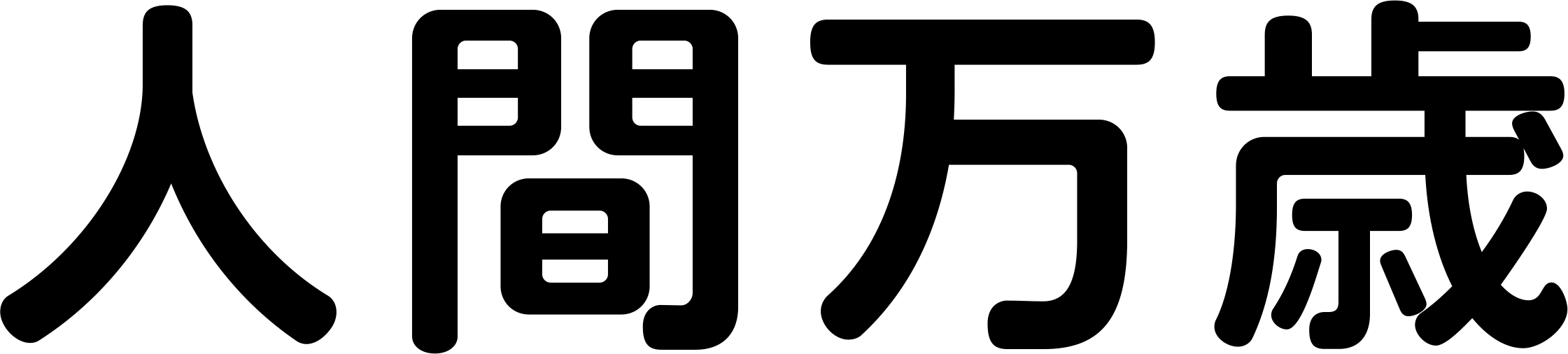自分が墓地になるんだよ
誰も思い出さなくなったら、それが本当の死
イントロダクション — なぜ「墓」なのか
人は紀元前から今のいままで「死んだらどうなるのか」をよく問う。宗教者は聖書や教典で答えを示し、哲学者は言葉を弄して概念を積み上げる。演説家は死を恐れるべきではないと声高らかに訴えかける。だが、それらの答えはどこか遠く、どこか他人事の匂いがする。私はそれを“身近な場所”に引き戻したかった――言葉や理論の外側にある、日常のもっと近い場所へ。だから私は墓へ向かった。
この作品は、抽象的な問いを「現実の風景」に落とし込む試みだ。171基の実在する墓を写真に収め、総柄として布に落とし込み、Tシャツという身体に近いメディアとして再編した。服としての「着る行為」が、記憶と忘却の境界に触れる小さな儀式になることを意図している。
制作の動機 — 見えないものを可視化する衝動
見えるものと見えないものの境界線は意外に薄く、日常の隙間にぽっかりと開いている。死後の世界についての議論は難しい言葉で飾られがちだが、墓がある場所だけは“誰かがここに在った”という確かな痕跡を残す。ならば、その痕跡そのものを集めて服にしたらどうなるか——その好奇心が、このプロジェクトの出発点だった。
私が着目したのは「お盆」という、御霊と現世が最も近づく期間だ。多くの地域でお盆は8月13日~16日に行われ、精霊馬であるきゅうりの馬と茄子の牛を仏壇に供え、迎え火と送り火で先祖を迎え、また送り出すと伝えられている。人々が墓を洗い、お花を供え、灯りを灯すその期間は、先祖と家族の記憶が一瞬だけ“戻る”時間だ。私はその「不在と在在の瞬間差」に着目した。
制作プロセス — 171基の墓と早朝の約束
この総柄の元となる墓は171基。すべて生成AIなんて安易なものではなく、「実在する墓」の写真だ。撮影はお盆の最終日、8月16日早朝5時に行った。夕刻に送り火を焚けばご先祖が墓に戻るため、早朝は“まだ帰ってきていない”可能性が高い時間帯だと考えたからだ。とはいえ「本当に誰もいない」と断言できるものではない。そこで私はひとつの視覚的なルールを設けた――生花やお供えがきちんとある墓だけを撮る、ということ。生花があるということは、13日に家族が迎えに来ていた証であり、その時間帯は不在である可能性が高い。花は目に見える「不在の証拠」だった。
撮影は静かな早朝、墓石の隙間を歩きながら、心の中で「今おられますか?」と声をかけた。写真を撮るときは、ただ記録するのではなく、丁寧に礼を尽くすように手を合わせた。撮影対象は無作為に選んだわけではない――凛と手入れされた墓、端正に花やお供えがある墓だけを選んだ。
倫理と了承 — 物語の共同制作としての配慮
「他人の墓を撮るなんて不謹慎ではないか」と考えるのは真っ当な疑問だ。私自身も同じ不安を抱えた。もし自分があの中の誰かなら、見知らぬ他人に墓を撮られて喜ぶだろうか、と。だから撮影前後の振る舞いは、創作上の重要なルールになった。
撮影からしばらくした9月22日、私は撮らせてもらった墓それぞれに挨拶をするために再度墓石の前に訪れた。線香をあげ、ここに収めたことへの報告と感謝を行ったうえで、御在宅の御霊に直接「Tシャツの柄にしても良いでしょうか」と尋ねたところ多くの方が温かく了承してくださり、心優しく受け止めてくださった。しかし中には「もしうちのもんがやめてくれと言ってきたら、それには従ってくれ」とおっしゃる方もいた。私はその約束を重く受け止め、必要があれば販売の停止やデザインの差し替えに応じる準備があることを返答している。
この行為は制作の独断ではない。写真に写る石碑とそこに宿る記憶、そしてその御霊とのやり取りを含めて、このTシャツは共同制作物である。服になる前に、許諾と祈りを差し出した
意味論 — 記憶、二度の死、そして服が担う役割
映画「リメンバーミー」で言及があるように、人は二度死ぬと言われる。ひとつ目は肉体の死、ふたつ目は誰からも思い出されなくなったときだ。生花が絶えない墓は、ご家族の記憶に生き、まだ二度目の死を免れている場所だ。写真として切り取られ、布地に落とし込まれたその墓は、別の形で記憶を延命する行為であるとも言える。
ただし、私の意図は単なる追悼や美化ではない。死と向き合うとき、私たちはしばしば不都合な感情や居心地の悪さと出会う。服として身につけることは、日常の生活の上でその居心地の悪さと向き合う小さな実験だ。墓が総柄として感化されることで、記憶は模様になり、柄になり、街の雑踏に紛れ込む。見た者は不意に立ち止まり、誰かを思い出すかもしれない。あるいは思い出すのをやめるかもしれない。どちらも等しく意味がある。
死と生、記憶と忘却、そして「二度目の死」を考えさせる一着です。
デザインについて — 見せ方と着せ方
総柄は近くで見ると石碑の凹凸や文字の影が読め、遠景になると抽象的なテクスチャとして機能する。これは意図的だ。墓が個であることと、集合的な風景になること、その両義性を一枚で表現したかった。プリントのトーンは基本的にモノクロに寄せ、祭礼の色彩や装飾を差し込まないことで静けさと重量を保っている一方で、供えられた「生花」だけはモノクロ化せず元の色彩のままを保っている。生花は御霊と現世をつなぐ架け橋であり、家族の想いの象徴だからこそ、色彩豊かに残すことで柄全体に「在る者の痕跡」を可視化する役割を持たせている。近くで見ると花の色が静かな点景となって立ち上がり、遠くから見ると墓石のテクスチャと彩度の差が微妙な緊張を生む——着る人は儀式を演じるわけではなく、ただ日常に故人の痕跡を連れて歩く。
着用上の提案と倫理的注意書き
このTシャツはユーモアの対象でも、単なるファッションの素材でもない。着るときは少しだけ、背中にあるもの、墓の重さを想像してほしい。もし街中で誰かが不快に感じたら、話を聞いてみてほしい。私たちは販売において故意に侮蔑や嘲弄を目的としていない。撮影対象となった方々やご遺族の気持ちを尊重することは制作の前提であり、万が一、当該家族や御霊が拒否の意を示した場合は、速やかに対応する。これも私たちの約束だ。
最後に
ファッションは物を覆うだけでなく、物語を携える装置でもある。このTシャツを選ぶという行為は、誰かの記憶を身に置くことと似ている。遊び心で着るならそれでもいい。重々しく敬意をもって着るならそれもいい。どちらの着方も、着る者の選択だ。重要なのは、記憶を単なる模様として消費しないこと。見ること、着ること、触れることを通じて、小さな問いを立て続けること。
「墓総柄Tシャツ」は、あなたに問いを差し出す服だ。問いにどう応えるかは、着るあなた次第です。